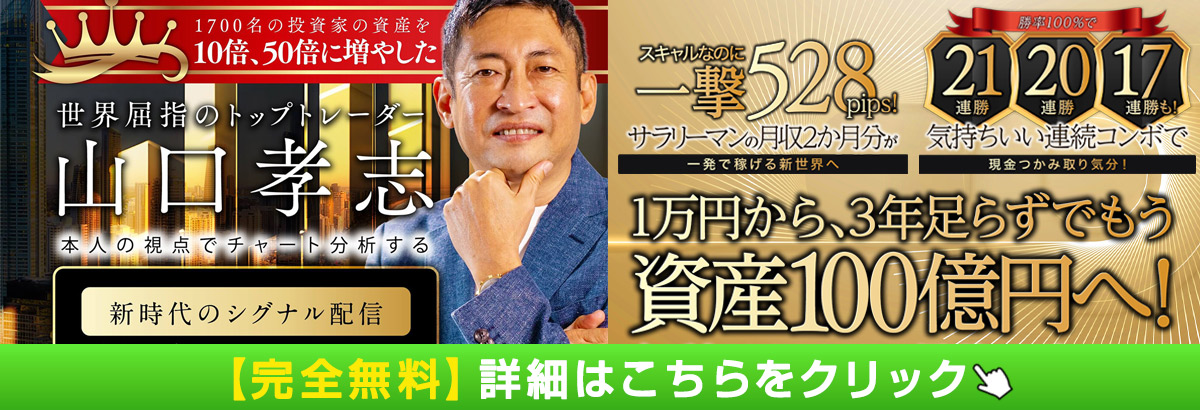[AD] 運営維持のため、一部広告リンクを設置する場合がございます(詳細)
FXは、売る時と買う時でレートが異なります。そして、この価格差の数字は、その外貨の買値と売値の差(乖離)を表していて、それを「スプレッド」と呼んでいます。
このスプレッドはトレーダーがFX取引をする際にかかるコスト(手数料)となり、このスプレッドが狭いほど取引コストが押さえられるので、トレーダーにとって大きなメリットになります。
しかし、FX初心者の方はスプレッドの意味を理解しないまま、口座開設をしてトレードをしている方がいます。
スプレッドのことを正しく知っていれば、資金を節約できたり、結果的に利益を多く増やすことにもつながるので、これからFXを始めようとする方は、スプレッドの特徴や基本的なことを必ず理解しておきましょう。
そこで、こちらの記事では、スプレッドの基礎知識や、取引の損益にどのように関わってくるのか詳しく解説していきます。ぜひ、参考にしてくださいね。
目次
FXにおけるスプレッドの意味とは?
スプレッドとは、直訳すると「広がり」といった意味を持ち、通貨を買う際に適用される買値(Ask)と、通貨を売る際に適用される売値(Bid)の間にある価格差のことを指します。
そして、この価格差というのが、FX取引をする上での実質的な取引コスト(手数料)に値します。
例えば、下記のドル円レートであれば「買値1ドル=110円744銭、売値1ドル=110円732銭」のように、買値と売値のレートが別々に提示されます。この場合、買値と売値の差(110.744円-110.732円=0.12円)がスプレッドとなります。
また、スプレッドの表現は一般的に「広い」「狭い」という言い方で表されますが、時々「高い」「低い(安い)」と表現されることもあります。
簡単に整理すると、こういった関係性が成り立ちます。
「広い」=「高い」
「狭い」=「低い(安い)」
普段使わない表現になると戸惑うかもしれませんが、スプレッドが高い=売値と買値の差が大きい、スプレッドが安い=売値と買値の差が小さい、と覚えておけば基本的に問題ないでしょう。
スプレッドの特徴
FXはメジャーな通貨からマイナーな通貨まで様々な通貨の取引ができます。
そして、スプレッドはFX会社や通貨ペアによって数値はそれぞれ異なりますが、一般的に流通量の高い通貨ペアはスプレッドが低く、流通量が少ない通貨ペアほどスプレッドが高くなる傾向にあります。
世界でもっとも流通量の多い通貨は「米ドル」で、その次に「ユーロ」「日本円」と続きます。そのため「ドル円」「ユーロ円」「ユーロドル」などのスプレッドはほとんどの証券会社で比較的狭くなっています。
逆に「トルコリラ」や「南アフリカランド」のように、流通量が少ない通貨ペアはスプレッドが広くなる傾向にあります。
日本人に馴染みのある通貨ペア「ドル円」は流通量が多いため、国内証券会社の場合、スプレッドはおおむね0.1銭~0.3銭と非常に小さな額となっています。
FX取引をするにあたって、スプレッド幅が小さいほどトレーダーにとって取引コストが低くなるため有利な取引環境になると言えます。なぜなら、スプレッドは取引をするたびに発生するので、取引回数が増えれば増えるほど、取引コストは積み上がっていくからです。
だからこそ、スキャルピングなどの1日に何度も重ねて利益を狙う取引スタイルの場合、スプレッドのコストが積み上がってしまうので注意は必要です。
※証券会社によってスプレッドの広さは違ってくるので、取引を行う前に必ずチェックしておきましょう。
スプレッドの計算方法
スプレッドの計算方法も合わせてお伝えします。
例えば、ドル円のスプレッドが「0.2銭」の場合だと、下記の計算になります。
[1万通貨の場合] 0.2銭×10,000通貨 = 2,000銭 = 20円
[1,000通貨の場合] 0.2銭×1,000通貨 = 200銭 = 2円
1万通貨で取引をした場合、0.2銭だとコストは20円となり、0.4銭の場合は40円、つまり0.1銭で1万通貨を取引をする場合、スプレッドは10円ということになります。
たった10円と思われたかもしれませんが、トレード回数が増えれば増えるほどトレーダーの取引コストとして積み重なっていくので、軽視してはいけません。
1万通貨取引で10円の取引手数料が掛かるということは、10万通貨取引なら100円となります。そして、これを1日100回トレードを行った場合、なんと10,000円も取引手数料が生じることになるのです。
また、100万通貨、1000万通貨とロット数を増やせば、それに応じて取引コストは増えていくため、ご自身の許容範囲でのロット数の調整と取引回数を心がけていくとよいでしょう。
スプレッドの「原則固定」の意味は?
基本的にスプレッドは証券会社が通貨ペアごとに固定幅で定めていることがほとんどです。
そして、このようにスプレッドを固定してレートを提供することを「原則固定」と表現します。
そもそも「なぜ、スプレッドを原則固定しているのか?」という点についてですが、スプレッドが小刻みに拡大したり縮小したり、つねに変動してしまうと、トレーダーが取引しづらいという理由から、証券会社はスプレッドを固定にしてレートを提供しています。
スプレッドが原則固定だと、トレーダーはスプレッドの拡大縮小により毎回取引コストが異なるということがなくなり、取引する通貨ペアの取引コストをあらかじめ把握したうえで、安心して取引をすることができます。
原則固定の例外
ただし、原則固定では提示通りのスプレッドを配信できない「例外」もあり、一時的にスプレッドが拡大することがあるので注意が必要です。
では、どのようなときに「例外」が起きるのでしょうか?大きく分けて3つのパターンがあるので、ご紹介します。
タイミング1:雇用統計などの重要な経済指標発表前後
米雇用統計や各国の政策金利発表などといった、重要な経済指標発表前は投資家が取引を控え様子見する傾向があるため、取引の流動性が低下します。
しかし、経済指標が発表されると注文が一気に増加し、価格が急激に動くことがあります。
証券会社は急激な価格変動に対応しきれない場合に、予定した価格で取引できないケースではスプレッドを広げて対応するため、重要な経済指標発表前後はスプレッドが広がりやすい傾向があります。
タイミング2:災害や要人発言などのビッグニュース
中央銀行総裁や大統領、政治家といった要人発言だったり、戦争やテロなどの国際情勢で大きな変化が起こると、その国の通貨の価格が急変することがあります。
相場急変動等によって、スプレッド幅が拡大、または、意図した取引ができない可能性があります。
最近では、新型コロナウイルスを引き金に起こったコロナショック相場や、米大統領選など大きなイベントによる相場急変時にもスプレッドが広がる傾向にあります。
タイミング3:明け方の時間帯、クリスマス時期
日本時間の朝5時~8時くらいまでの間は、世界の主要なマーケットが開いていない時間帯なので、市場参加者が少なく流動性が低下することからスプレッドが広がる可能性があります。
また、クリスマスや年始年末は海外の投資家が長期休暇を取って相場から離れる傾向があるため、取引量が大幅に減って流動性が低くなることでスプレッドは不安定になります。
スプレッドが広がっても、トレードスタイルによっては影響を受けないこともありますが、トレードを有利に進めていくためにも、上記3つは必ず覚えておきましょう。
スプレッドの見方について
では、実際の取引画面でスプレッドを見てみましょう。
MT4でスプレッドを確認するためには「気配値表示」→「右クリック」→「スプレッド」をクリックすると、赤枠で囲んだところにスプレッドが表示されます。
こちらの表示されている数値は、買値(Ask)の値から売値(Bid)の値を引き算しているだけのポイント表示なので、数値が「12」であれば「1.2pips」となり、これがその通貨ペアのスプレッドとなります。
上記の場合だと各通貨ペアのスプレッドは、
USDJPY:1.2pips、EURUSD:1.2pips、GBPUSD:1.3pips、EURJPY:2.0pips
GBPJPY:2.2pips、EURGBP:2.3pips、AUDUSD:1.6pips、AUDJPY:2.1pips…etc
このようになります。
特に証券会社のスプレッドを比べたい時には、それぞれの証券会社のMT4を起動させて横に並べると、スプレッドの違いを把握することができます。
また、MT4のチャート画面上にある下記のボタンは「2ウェイプライス」(ツーウェイプライス)と言われるもので、それぞれ「お客様が売ることができる価格(買値)」と「お客様が買うことができる価格(売値)」の2つの価格が提示され、こちらからもスプレッドを確認することができます。
わざわざ気配値を開いてスプレッドを確認することなく、現在のスプレッドの広がりがひと目で分かるため、慣れてきたら、こちらでおおよそのスプレッドの広がりを把握すると良いでしょう。
口座ごとのスプレッド12社比較
スプレッドは金融機関の判断で自由に定められるもので、証券会社によってスプレッドの設定には違いがあります。
例え、1通貨単位ではわずかな差であっても、レバレッジをかけてそれなりの規模の取引を行えば、大きなコストの違いを生むことになるので、取引コストはFX会社を選ぶ際の重要な要素の1つとなります。
そして、ここからは各FX会社のスプレッドを比較していますので、FX会社選びで迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
メジャー通貨のスプレッド比較表
| ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | ユーロドル | ポンドドル | |
| GMOクリック証券 | 0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | 0.7銭 | 1.2銭 | 0.4pips | 1.0pips |
| YJFX! | 0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | 0.7銭 | 1.2銭 | 0.4pips | 1.0pips |
| DMM FX | 0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | 0.7銭 | 1.2銭 | 0.4pips | 1.0pips |
| ヒロセ通商 | 0.2銭 | 0.4銭 | 1.0銭 | 0.6銭 | 0.8銭 | 0.3pips | 0.6pips |
| 為替ジャパン | 0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | 0.7銭 | 1.2銭 | 0.4pips | 1.0pips |
| 外為オンラインFX | 0.1銭 | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.3銭 | 0.6銭 | 0.1pips | 0.3pips |
| LIGHT FX | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.9銭 | 0.6銭 | 1.0銭 | 0.3pips | 0.8pips |
| インヴァスト証券 | 0.3銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | 0.6銭 | 1.7銭 | 0.3pips | 1.4pips |
| FXブロードネット | 0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | 0.6銭 | 1.3銭 | 0.3pips | 2.9pips |
| セントラル短資FX | 0.1銭 | 0.4銭 | 0.9銭 | 0.4銭 | 0.9銭 | 0.3pips | 0.8pips |
| FXプライム | 0.3銭 | 0.6銭 | 1.1銭 | 0.9銭 | 1.6銭 | 0.6pips | 1.8pips |
※スプレッドは原則固定(例外あり)
※本コンテンツの調査対象は法人口座ではなく、すべて個人口座となっています。サービス内容は当社が独自に調査したものです。正確な情報を提供するよう努めておりますが、詳細は各FX会社にお問い合わせください。
「銭」と「pips」の違い
ほとんどの証券会社が採用するスプレッドの単位は2種類です。それが「銭」と「pips」です。
取引する通貨ペアの対象が「外貨/日本円」の場合、つまり、通貨ペアの片方が日本円の場合、スプレッドは「銭」という単位を使う証券会社が多いです。
しかし「EURUSD(ユーロ米ドル)」や「GBPUSD(ポンドドル米ドル)」のように、通貨ペアが日本円以外のものありますので、そうしたケースも踏まえ、日本円を含む通貨ペアとそうでないペア共通のレート単位、それが「pips」となっています。
各証券会社によって表記は違いますが、意味合いは同じなので安心してくださいね。
スプレッドの低い証券会社を使おう
スプレッドについて詳しく解説してきましたが、なぜ証券会社によって、このような差が存在するのでしょうか?
答えはシンプルなのですが、スプレッドはFX業者の収益(仲介手数料)になるからです。
そのため広くとも狭くとも、毎回のトレードで必ずスプレッドは引かれ、取引したらスプレッド分よりも多く利益を出さないと、収益はプラスになりません。
つまり、トレーダーにとってスプレッドは狭ければ狭いほど、多くの利益につながるので非常に重要です。
また、先ほどもお伝えしたように、スプレッドは原則固定となっていますが、証券会社によっては、時間帯によりスプレッドが広がったり、狭くなったりします。
特に取引が活発な時間帯では、注文が一度に集中するため仲介の証券会社のやり取りが追いつかなくなり、結果的に注文価格が異なる(滑る)という事態が起こります。
その場合、証券会社が滑って動いてしまった分の差額を補填しなくてはなりません。
よって取引が活発な時間帯になると、証券会社がスプレッドを意図的に広げ、トレーダーからの注文を少なくすることもあります。
このように、証券会社の都合でスプレッドが広がる可能性があるのであれば、やはり、トレーダーは最初からスプレッドの低い証券会社を選んだほうが、不要な手数料を毎回支払わなくて済むので断然お得と言えるでしょう。
スプレッド意味:まとめ
これまでお伝えしてきた通り、スプレッドはFX取引において軽視できないものです。
一見小さな金額に見えるかもしれませんが、取引回数が増えれば増えるほど、そしてFX取引を長く続ければ続けるほど、取引コストは蓄積されていきます。
しかし、低いスプレッドを提供している証券会社を選んで取引をすれば、取引の際にかかるコストを長期的にも押さえることにつながります。
ただし、原則固定となっていても適用の範囲は証券会社によって異なり、場合によっては適用されないこともあるので注意しましょう。
あなたもこの記事をきっかけに、今一度使っている証券会社を見直してみてはいかがでしょうか?
こちらのページでは、FX取引が行える日本の証券会社を中心に紹介しています。
日本にある証券会社の多くを網羅しており、それぞれのメリットやデメリットを個別で解説していますので、ぜひともご自身にあった証券会社を見つけてくださいね。
 豪ドルの5年後見通しは?100円超えの可能性や相場分析から見る買い時とは【2022年最新】
豪ドルの5年後見通しは?100円超えの可能性や相場分析から見る買い時とは【2022年最新】